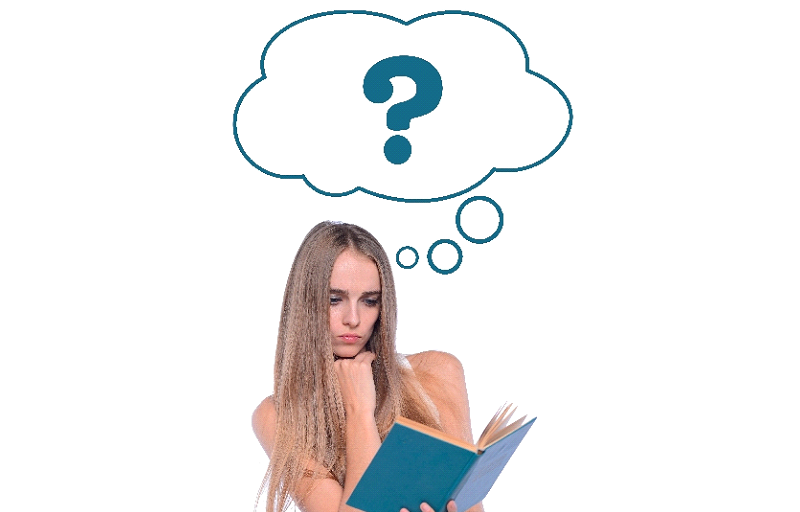最近、よくその名を耳にするようになったDHA・EPAという成分。
今回は、DHA・EPAとはいったい何なのか?その効果や働きと、効果的に摂取する方法をご紹介します。
目次
DHA・EPAって何?
DHA・EPAは脂肪酸の種類
DHAとEPAを知るために、まず脂肪酸という栄養素についてご説明します。
脂肪酸とは、三大栄養素の一つである脂質を作る成分です。
脂質は、私たちが活動するためのエネルギー源となったり、細胞の原料となります。
脂肪酸は、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられ、不飽和脂肪酸はさらに一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸に分けられます。
飽和脂肪酸は常温で固まりますが、一価脂肪酸は常温で液体を保ちます。
多価不飽和脂肪酸は常温では柔らかい状態か、液体として存在します。
DHAとは
DHAはドコサヘキサエン酸の略称で、多価不飽和脂肪酸に属します。
また、DHAは必須脂肪酸という体内で合成できない脂肪酸です。
体内では脳や目などに多く含まれます。
EPAとは
EPAとは、エイコサペンタエン酸の略称で、DHAと同じく多価不飽和脂肪酸に分類されます。
EPAも必須脂肪酸の一つです。
体内では、主に皮膚に存在しています。
実は体内で作れる?
DHAとEPAは厳密にいえば、体内に取り入れられたα-リノレン酸という脂肪酸から合成することができます。
しかし、そのα-リノレン酸自体は体内で合成できず食品からの摂取に頼っているため、DHA・EPAともに体内で合成できない必須脂肪酸と位置付けられています。
ちなみに、α-リノレン酸からDHA・EPAが合成される割合は10〜15%程度です。
さらに、体内ではEPAからDHAも合成することができますが、その合成効率はとても悪く、ほとんど合成することができないといって良い程なのだそうです。
DHAとEPAの働きって?
では、DHAとEPAは何が違うのでしょうか?その働きを見てみましょう。
DHAの5つの働き・効果効能
1、脳を活性化させる
脳には、有害な薬物や毒物が入らないようにする血液脳関門と呼ばれる機構があります。
DHAはその血液脳関門を通ることができる成分だということが大きな特徴です。
脳の細胞を作っているのは細胞膜で、DHAがその細胞膜を柔らかくしてくれています。
また、DHAは脳の中で情報伝達機能を受け持っているシナプス膜という物質を作る材料になっていることから、DHA はシナプスが情報を伝達するために重要な役割を担っています。
DHAのこれらの働きにより、記憶力や観察力、判断力が良くなることが分かっています。
DHAが十分にあれば脳は活発に働きますが、年齢とともにDHAは減少してしまうため、これが認知症の一因といわれています。
アルツハイマー型といわれる認知症では、脳の神経細胞が死んで萎縮してしまいますが、DHAは神経細胞を修復して、残った神経細胞の働きを助けることも分かっています。
つまり、DHAは認知症予防にも効果があるということです。
2、血流を良くする
DHAには中性脂肪の濃度を下げる働きがあり、血液の粘度を下げて血流を良くしてくれます。
また、血管壁や赤血球の細胞膜を柔らかくする働きもあり、血流の改善や血圧が高くなるのを防いでくれるそうです。
血流が良くなることで、動脈硬化を予防し、結果的に脳梗塞や心筋梗塞の予防にも効果があると期待されています。
3、アレルギーを予防する
アレルギーが起こるのは、アレルギー物質に対する抗体に、体内でつくられた化学物質が反応するためです。
この化学物質はプロスタグランジンと呼ばれ、アトピー性皮膚炎や花粉症,喘息といったアレルギー症状や関節炎などの炎症を起こすと言われています。
このプロスタグランジンの働きを促進するのが、シクロオキシゲナーゼという酵素です。
DHAには、このシクロオキシゲナーゼを阻害し、プロスタグランジンがつくられるのを抑制する働きがあります。
したがってアレルギー症状や関節炎などを緩和に繋がります。
4、視力を回復する
目の網膜にも脳と同じように、血液網膜関門という機構があります。
DHAはその血液網膜関門も通過することができ、視力を良くするために大切な成分になっているということが分かっています。
また、視力低下の一因に脳の働きが鈍くなることも挙げられることから、脳の働きを活性化するDHAを摂取すると、近視や動体視力の改善などに効果があるといわれています。
5、神を安定させる
脳内にはセロトニンという感情をコントロールする働きのある物質が存在します。
セロトニンはイライラしたりカッとしたりするのを抑えてくれる働きがあるほか、不足するとうつ病になりやすいことが知られています。
まだはっきりとは分かっていませんが、DHAを摂取することで脳内のセロトニンの働きを高める可能性があることが研究によって分かりつつあるそうです。
EPAの4つの働き・効果効能
1、血流を良くする
EPAには高い血小板凝集抑制効果があることが大きな特徴です。
これは、血液が固まるのを防ぎ血栓をつくらせないようにする働きのことで、血液の流れをスムーズにします。
また、赤血球の膜を柔らかくしたり、血管を柔らかくしなやかにする作用があります。
血流が良くなることで、動脈硬化や高血圧を予防し、その結果、脳梗塞や心筋梗塞などのリスクを下げる効果があります。
2、炎症・アレルギーを抑制する
炎症とは、有害な物質に対する生体の防御反応の事です。
炎症が起こった時に生体が引き起こす、腫れや痛み、発赤などの反応を炎症反応と呼びます。
アレルギーも炎症反応の一つです。
この炎症を起こす原因のひとつにアラキドン酸という脂肪酸があります。
アラキドン酸自体は体内に必要な必須脂肪酸の一つですが、過剰に作られることで人体に悪影響を及ぼします。
EPAにはこのアラキドン酸の過剰な合成を抑えて炎症を抑える働きがあります。
また、EPAにもDHAと同様にアレルギー症状などの炎症の原因となるシクロオキシゲナーゼなどの酵素を抑制する働きがあります。
したがって、アレルギーや喘息、慢性気管支炎などの炎症性疾患の改善にも効果があります。
3、精神を安定させる
EPAにもDHAと同様にセロトニンの働きを高めて感情をコントロールする可能性があることが分かってきています。
4、ダイエットに効果がある
EPAにはGLP-1というホルモンの分泌を促進させる働きがあります。
GLP-1には食欲をコントロールしたり、血糖値の上昇を緩やかにしたり、インスリンの分泌を促進する作用があります。
したがって、EPAがダイエットにも効果があると注目を集めているそうです。
DHAとEPAの違い
DHAとEPAの働きをみると、どちらも同じような働きがあり、どちらも体に良いことがわかりました。
では、DHAとEPAは何が違うのでしょうか?
脳と眼に良いのはDHA
両者の働きで挙げたように、DHAは血液脳関門と血液網膜関門を通過できますが、EPAは通過できません。
そのため、脳や眼といった神経系によく働いてくれるのはDHAということになります。
血流に良いのはEPA
両者とも血流を良くしてくれる働きがあることはご説明しましたが、血栓を防いで血液をサラサラにする効果のあるEPAの方が、血流を良くする働きがDHAより高いといわれています。
ダイエットならEPA
EPAが持っているGLP-1の分泌を促進する働きは、DHAにはなくEPA独自のものです。
なので、ダイエットに効果的なのはEPAといえます。
子供・妊婦・高齢者にはDHA
DHAは脳の神経系を活性化させる働きがあるため、成長期の子供や胎児の脳を成長させてくれたり、高齢者の認知症を予防してくれます。
なので、子供・妊婦・高齢者にはDHAがより必要といえます。
DHAとEPAの効果的な摂取方法
必要摂取量
2010年版の「厚生労働省 日本人食事摂取基準」によれば、DHA・EPAとも1日1g(1000mg)以上の摂取が望ましいとのことです。
では、1日1000mgを摂取するにはどうしたらよいのでしょうか?
DHAとEPAが多く含まれる食材は?
DHA・EPAともに、多く含まれるのは「脂ののった青魚」です。
例えば、サンマ・ブリ・サバ・イワシ・マグロなどに豊富に含まれています。
効率良く摂取するには、脂ののったお刺身を食べるのが良いそうですが、焼き魚や缶詰めなどでも摂取できます。
ちなみに、サバ100gにDHAは1781mg、EPAは1214mg含まれています。本マグロ100gにはDHAは2877mg、EPAは1288mg含まれています。
効果的に摂取するには
DHA・EPAは溶けやすいので熱に弱く、調理にする際は注意が必要です。
せっかく青魚を食べようとしても、煮たり焼いたりするとおよそ20%の栄養分が、揚げ物にすると半分近くの栄養分が溶け出してしまうのだそう。
とはいえ、毎日お刺身ばかりでは長続きしませんので、煮物にするときは煮汁ごと食べるたり、ホイル焼きなどで栄養が逃げないようにして、なるべく毎日摂取することを心がけましょう。
一緒に摂ると良い食材
DHA・EPAは体内で酸化しやすい栄養素なので、抗酸化作用のある食品と一緒に摂取するのが好ましいです。
抗酸化作用の高い栄養素で代表的なのはβ-カロテン(モロヘイヤ、にんじん、パセリ、ほうれん草など)、ビタミンC(ブロッコリー、パプリカ、アセロラなど)、ビタミンE(あんこうのきも、すじこ、落花生、モロヘイヤなど)などです。
DHA・EPAを摂取する際は、これらを一緒に摂取することを心がけることでDHA・EPAが酸化しにくくなり、吸収されやすくなります。
さらに、ワインなどに含まれるポリフェノールや、ゴマに含まれるセサミンという栄養素なども抗酸化作用があると分かっています。
一緒に摂らない方が良い食材
DHA・EPAは青魚の油脂に多く含まれます。
油脂は、小腸を通過するときに体内へ吸収されるのですが、その吸収を阻害するのが食物繊維です。
ダイエットのために食物繊維を多く摂るようにしている方もいるかもしれませんが、DHA・EPAを効果的に摂取したいのであれば、食物繊維と一緒には食べないほうが良いでしょう。
DHAとEPAのサプリメント
魚が嫌い、青魚アレルギーなどの理由でDHA・EPA不足が気になる方や、毎日青魚ばかり食べられないという方もいると思います。
そんな方のために、今は効果的に摂取できるサプリメントがたくさん市販されています。
もちろん、サプリメントは食事の補助ですから、基本はバランスの良い食事を摂ることはお忘れなく。
青魚にアレルギーのある方でも、DHA・EPAのサプリメントは服用できるそうです。
しかし、念のため医師に相談しておくと安心ですね。
ただしDHA・EPAは1日3000g以上の摂取で血液が固まりにくくなり、出血しやすくなるという副作用がありたくさん摂ればよいということではないので、サプリメントを用いる場合は服用量を守るようにしましょう。
さいごに~DHA・EPAの摂り溜めはできない~

DHA・EPAの働きや効果的な摂取方法についてご説明しました。
DHA・EPAは心身ともに健康でいられるために、どの世代の方にも非常に役立つ栄養素です。
しかし、一度にたくさん摂取しても、体内に溜めておくことはできません。
また、一度摂取したからといってその効果を実感できるものでもありません。
毎日コツコツと、日常生活に取り入れることで効果を発揮してくれることを念頭において、効果的な摂取を心がけましょう。