温度差が激しい今の季節、とても風邪をひきやすい時期ですよね。
しかも一度風邪をひいてしまうと、なかなか治らない事も少なくありません。
そんな風邪の症状の中でも厄介なのが、咳です。
しゃべりたいのに咳が邪魔してなかなかしゃべれない…笑いたいのに咳ばかりで存分に笑えない…
風邪が治っても長引くこともある咳の対処法を、ご紹介していきます!
目次
咳が出るのはなぜ?

風邪の主な症状として知られている、咳。
咳が出るのは、体内に侵入してきたウイルスや細菌を体外へ排出するためです。
これらを排出するための防衛反応としては、鼻水も挙げられますね。
特に咳は、粘膜についてしまったウイルスや細菌を排出するための防衛反応と言えます。
のどや気管、気管支、胃、横隔膜などが刺激を受けると、咳が出るのです。
咳に痰が絡むのはなぜ?
咳の症状と共に良く聞かれるのが、痰(たん)です。
風邪をひくと、痰が絡んだ咳をする事が多くなりますよね。
そもそも痰とは、体内に侵入してきたウイルスや細菌の死骸を含んだ気道分泌物なんですよ。
私たちの気道は、元々空気の通り道となっています。
しかし空気の通り道は、同時にウイルスや細菌の侵入口ともなりやすくなっています。
ウイルスや細菌が気道に侵入してくると、気道の粘膜が多く分泌される事になります。
そして、ウイルスや細菌を包み込んで痰となるんです。
ちなみに一般的な痰は、黄みがかった色をしています。
しかし他の色が強い場合には、風邪ではない病気の可能性もあるので早めに医療機関での診察を受けていきましょう。
この痰が咳に絡むのは、咳によって痰を体外へ排出しようとしているからです。
咳は体内の異物を体外へ排出するためのものなので、痰も異物に該当する訳なんですね。
つまり咳に痰が絡むのは、正常な防衛反応と言えるんです。
しかし咳が3週間以上治らずに続いている場合には、感染症の病気などの疑いがあります。
また血が混じっていたりする場合も、なるべく早めに医師の診察を受けていきましょう。
咳がひどい時は薬が良い?

薬局には、実に様々な風邪薬が並んでいますよね。
咳を止める薬も、多くの種類が販売されています。
咳がひどい時には、もちろんこうした市販の薬も有効です。
日常生活にも支障が出てくる様な咳の場合には、ぜひ薬の力も取り入れていきたいですよね。
しかし病院へ行く時間があるのであれば、ぜひ医師の診察を受けて処方箋の薬をもらっていきましょう。
市販薬よりも、処方箋の方が断然効果は高くなっています。
そして市販薬よりも安く済む場合が多い上に、症状に合った薬を処方してもらえます。
そのため、可能ならば病院での診察を受けていく方が良いと言えるんですよ。
市販薬で即効性があるのは?
咳止め薬には、市販薬でも様々なタイプがあります。
錠剤や粉薬、カプセル、スプレー、シロップ、液剤など、どれを選んだら良いのか迷ってしまいますよね。
中でも比較的効果が早く出て即効性があるとされるのは、スプレーやシロップ、液状タイプです。
特にシロップや液剤は、錠剤やカプセルなどよりも体に吸収されやすいので効果が出るのが早いとされているんですよ。
これらの薬は保管期間が短いのが難点ですが、即効性を求めるのであればこうしたタイプの薬を選ぶのも良いですね。
基本的には、自分の体質や好みに合う薬を選んでいきましょう。
咳におすすめの食べ物は?
なるべく薬に頼りたくない!という人には、咳に効果的な食べ物を積極的に摂っていきましょう。
例えば、長ネギです。
昔から咳に効果があるとされてきた長ネギですが、緑の部分には栄養が多く白い部分には咳を止める薬効成分が多いとされているんですよ。
焼いたり鍋にいれて食べたりする他、焼いた長ネギをガーゼでくるんで喉に巻くのもおすすめです。
その他にも、生姜や大根、レンコンもおすすめの食材です。
またカリンやキンカン、カモミール、ペパーミントなどもおすすめですが、これらは飲み物にして飲んでいくと良さそうですね。
さらに、オリーブオイルも咳に効くとされているんですよ。
オリーブオイルをスプーン一杯飲むと、咳が和らぐとされているんです。
しかしなかなかオリーブオイルをそのままというのは、難しいですよね。
そんな場合には、オリーブオイルにはちみつなどを混ぜて飲んでみるのも良さそうです。
咳を止める方法6選!

辛い咳は、実は簡単な方法で止めることができます。
しかし人によって効果の持続時間は異なってきますので、様々な方法を試して自分に合うものを探してみると良いですね。
1.加湿する
咳は、乾燥した状態になるとひどくなってしまいます。
それと言うのも、ウイルスや細菌は乾燥した環境で活発に活動するからなんですよ。
活発となったウイルスや細菌は、どんどんと体内へと侵入してきてしまいます。
さらに乾燥によって気道の粘膜も乾いてしまうので、咳が出やすくなってしまうんですね。
そのため、乾燥しない様に加湿する事はとても大切と言えるんです。
2.マスクをする
風邪予防などでよく使用されるマスクですが、咳を止めるためにも大活躍します。
マスクをする事で、自分の吐いた息で加湿効果が得られるんです。
これならば、加湿器がない乾燥した環境でも加湿する事が可能ですよね。
また咳をしていてもマスクをしていれば、マナーとしても良いものです。
そのため、咳が出る時にはマスクをしていると一石二鳥と言えますね。
3.湯船に浸かる
風邪をひいた時はお風呂を控える様に、と言われる事もあります。
しかしこれは、基本的にお風呂あがりに湯冷めしてしまう事と体力を消耗してしまう事が理由と言われているんですよ。
そのため咳だけの症状で体力に問題がないのであれば、ぜひ湯船にゆっくり浸かっていきましょう。
お風呂は体内をしっかりと潤してくれる、最高の環境なんです。
ただし、湯冷めしない様に十分に注意していかなければなりません。
また、お風呂あがりには水分補給も忘れずにしていきましょう。
4.水分をたっぷり取る
体内を乾燥させないためには、水分補給が欠かせません。
こめまに少しずつ水分をとって、体内が乾燥しない様にしていく必要があるのです。
また水分はなるべく常温のものを選び、喉に刺激を与えない様にしていきましょう。
5.はちみつ
はちみつには殺菌作用があり、風邪や咳にも大変効果的と言われています。
はちみつはそのまま食べても良いですし、お湯で溶いて飲むのも良いですね。
大変甘いので、美味しく食べられて咳を抑える事もできるので嬉しいものです。
しかし、1歳未満の乳児には与えない様に注意しなければなりません。
1歳未満の乳児は、はちみつによって乳児ボツリヌス症を発症してしまう可能性があるのです。
1歳以上であれば、はみちつは非常に体に良い食べ物となっているんですよ。
6.喉を温める
喉を温めるのも、咳を止めるのには良い方法です。
室内でも、マフラーやネックフォーマーを使って喉を冷やさない様にしていきましょう。
喉が冷えると、咳は出やすくなってしまいます。
マスクをしてマフラーなどで喉を温められれば、咳対策効果は大変大きいと言えそうですね。
夜に咳がひどくなる場合の対処法は?

日中はもちろんながら、夜寝る時に限って咳がひどくなるという事もありますよね。
しっかりと眠りたいのに、咳のせいでなかなか寝付けないなんて事も多いものです。
これは、寝る時になると副交感神経が活発になり筋肉が緩む事が関係しています。
筋肉が緩むと、気道がどんどんと圧迫されてしまうんです。
すると気道が狭くなって、咳が出やすくなるという訳なんですね。
この場合には、温かい飲み物やはちみつを口にしてから寝るというのも咳を緩和させるのに効果的です。
またマスクをするのも、加湿できるので効果的なんですよ。
それ以外にも、下記3つの方法が寝る時の咳には有効となっています。
1.横向きに寝る
仰向けに寝ていると、気道が狭くなりやすくなってしまいます。
気道が狭くなればなるほど、咳はひどくなりやすくなってしまうんです。
そこで、気道が開きやすくするために横向きに寝てみましょう。
横向きになる事で、気道が狭くなりにくくなるので効果的ですよ。
2.枕を高くする
枕をいつもより高くするというのも、咳を鎮めるには効果的です。
上体が高くなる事によって、気道が狭くなりにくい姿勢にする事ができるんですよ。
この時枕だけを高くしてしまうと、頭だけが高くなってしまって逆に気道が狭くなってしまう事もあります。
そのため、背中あたりから徐々に高くしていくと効果的ですよ。
3.飲酒を控える
お酒を飲むと、筋肉が緩みやすくなる事が分かっています。
筋肉が緩むと気道が狭くなりやすいので、咳が出やすくなります。
飲酒をして寝ると、いつもよりも寝る時に気道が狭くなりやすくなってしまうんです。
そのため特に咳がひどい場合には、飲酒を控える様にしましょう。
また、タバコも控えると咳には効果的ですよ。
まとめ
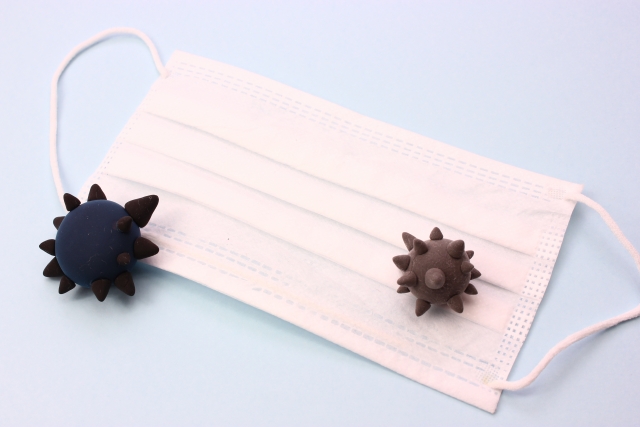
風邪の症状としても代表的な咳は、日常生活に大きな支障を与えるものです。
言いたい事も咳に邪魔されて伝えられないのは、本当に辛いものですよね。
そんな咳には、加湿や体を温める方法が有効です。
加湿器を使って加湿する方法だけでなく、マスクを使うなど身近なアイテムでも加湿は可能なんですよ。
これからの時期は特に、暖房機器の使用により乾燥しやすい時期となります。
それに伴って咳の症状も出やすくなるので、日頃から加湿をしておく事もとても大切ですね。
また夜は、どうしても咳がひどくなりやすい時間帯です。
咳で寝にくい夜は、寝方や枕の高さなどを工夫してみると良いかもしれませんよ。
そして食べ物や飲み物、時には薬を利用していくのも効果的です。
特にはちみつは、殺菌作用があるので咳には大変効果的と言われているんですよ。
様々な対策方法がありますが、その時の状況や体質に合わせてより良い方法を取っていけるといいですね!