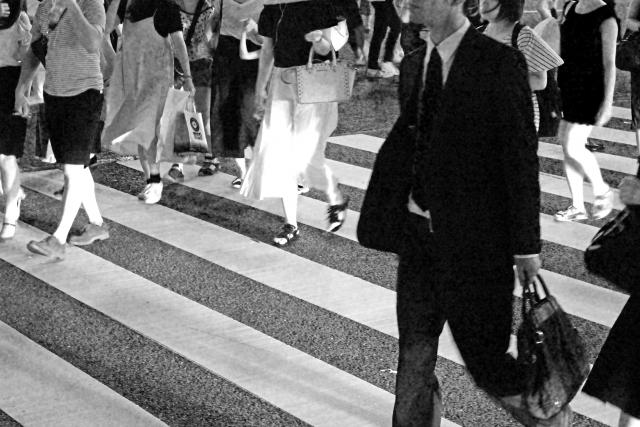春は新入社員や人事異動でバタバタする日が続きますが、少し落ち着いた5月になっても環境の変化についていけず、5月病と言われる憂鬱な気分に陥ってしまう方があります。緊張が高い状態が長く続くと、誰でも精神的にも肉体的にもつらくなってくるものですよね。辛い気持ちを一人で抱え込まないように、5月病の原因を理解して、自分でもできる改善方法をご紹介していきましょう!
目次
5月病ってなに?
5月病という言葉はいつ頃から来たかというと、昭和23年に祝日法が施行され、GWという大型の長期休暇が登場したころからと言われています。精神的な緊張を強いる4月を抜けてやっと業務や環境に慣れようとした頃に、大型連休がやってきて慣れた気持ちに歯止めがかかってしまうことで起こるとか。
5月病は、医学的にはこういった名称の病気はなく、精神的な状態を表すようです。「4月当初はあんなにやる気がでていたのに、連休後になると急にやる気がなくなり、不安ばかりが増してきた」とか「大型連休で羽を伸ばす気力もなく、家から一歩もでられなくなった」など症状は様々です。
いずれにしても、4月当初から緊張し続けた神経が、5月になると肉体的にも精神的にも十分疲労しているのはまちがいありません。ストレス解消を上手にしている方や、過度に自分を責めないようにできれば随分と楽なのでしょうが、まじめな方や完璧に仕上げたいと思う完璧主義の方にとっては、心が休まらない日々が続くのかもしれませんね。
就職してから無気力になったり、職場に行く足が遠のいたりする場合は、少しだけ息抜きが必要なのかもしれませんよ。5月病という言葉があると、自分もだと思いがちですが、あなたは本当に5月病なのでしょうか?
こんな症状があったら5月病かも!詳しい症状は?
新しい職場に配属されると、終わることのない仕事の山や人間関係の複雑さから、急激に無気力になったり、出社拒否になったりすることがあります。こうした特徴的な症状は、精神的なものと身体的なものとがあります。
精神的な症状
5月病の多くは精神的につらい症状が続きます。
- 急に不安に襲われて気持ちをあげることができない気持ちが続く
- 一度落ち込むと元に戻せないほど長く落ち込む
- なんとなく焦ってばかりで前に進めない状態になる
- 不眠が続く
- めまいが酷くなる
- 無気力で何もやる気が起こらない
- 不安、抑うつ、焦り
- 不眠、めまい、動悸
など精神的なものから、あちこちに自律神経系の身体の不調が現れていきます。
肉体的な症状
5月病といえば、たいていが精神的な面で落ち込んだり、わけもなく辛くなったりするので、まさか身体にも影響があるとは思われないかもしれませんね。ところが精神的な症状の他にも、身体的な症状もあるのです。
身体的に起こる5月病の症状としては
- 胃の痛み、動悸、めまい、風邪のような症状が続く
- 食欲がなくなる
- 下痢、全身倦怠
などがおこることがあります。こういった症状は、身体が不調の時にも単発で起こることがありますので、5月病とは鑑別しておきたいですね。
5月病と思っていたら本当はうつ病なのかも?
5月病の症状は、うつ病と似ているところがあります。ところが5月病というのは、緊張が多い新しい環境の変化についていけず、精神的に追いつめられた気分障害や不安障害(適応障害)などと病院では診断されています。
新入社員がたまたま憂鬱な気分を5月に感じていると、まわりの人が「5月病かもしれないね」と口癖のように言うこともありますよね。本当は5月病ではなかったり、もっとひどいうつ病にかかっているのかもしれません。きちんとした鑑別はしておきたいですね。
5月病は?
5月病はうつ病とはちがって、4月の新学期や新社会人生活の始まりから、最初は張り切ってやりきれていたのに、急激な環境の変化に対応できなくなって、連休明けごろからやる気がなくなってしまうといった状態が「5月病」になります。たいていは、1~2ヶ月もすれば環境に慣れてきて、5月病の症状がなくなっていきます。
うつ病は?
ところが5月病の精神的な症状が、いつまでたっても良くならなかったりすると、うつ病を疑ってみることも大切です。うつ病が5月病と違うのは、気分の落ち込みが長期間継続し、憂鬱感や不眠、意欲が全くなくなる、いくら考えようと思っても頭に入らないといった頭の回転が鈍ってくることが特徴の一つです。またさらにひどい場合には、決断力の低下や記憶力の低下、物忘れがひどいなど、ボケてしまったのかと思うほど、思考が停止していきます。
うつ病になる前は、イライラが強く人にあったりすることが多かったり、全身の疲労感や、不安でたまらなくなったりすることがあります。急激な体重低下がおこったり、起きることだけでも困難で、身体になまりが入っているほどだと表現される方もありますね。このように精神的にも肉体的にも、もうこれ以上頑張れないという状態を、さらに無理にがんばったために起こるものが多く、「心の風邪」とも言われています。
5月病が悪化して、うつ病になってしまった場合には、心療内科や内科を受診して適切な診断をして、治療するのが大切です。
5月病になりやすいタイプ
5月病になりやすいタイプがあるようです。特徴的なタイプをいくつか挙げてみましょう。
- 精神的に自分を追い詰めてしまう
- 完璧主義
- 真面目
- おとなしい
- 几帳面
- 責任感を一人で背負ってしまう
- 感情表現を表にだすのが苦手
- 気配りやきずかいし過ぎる
- 我慢強く忍耐力がある
といった方に多いようです。こうした特徴を持つ方が全て5月病にかかるわけではありません。5月病になりやすいタイプの方が、過度のストレスにさらされても、上手にストレスを解消できれば、ならない可能性の方が高いです。
5月病の原因は?
5月病になるタイプには特徴があることがわかりましたが、こうした元々もっている性格的な思考が災いして、5月病に陥るケースが多いようです。ものごとをどうとらえて、どう解決していくかを真面目に考え、自分ひとりで解決しようとするような、他人に迷惑がかけられないという遠慮がちな方は、5月病にかかりやすいようです。
また、新しい環境で新しい事柄を学んでいくときに、誰でも失敗はあるものですが、その失敗をいつまでもひきずってしまうタイプの方は、自ら苦しみを作って、一つの失敗でつまづいてしまい、ストレスを抱えてしまいます。
5月病になってしまった時の対処方法は?
5月病になってしまったと感じるときには、睡眠時間をたっぷり摂ることが大切。一日の睡眠時間が6時間あったとしても、睡眠時間のサイクルが夜間に移行していた場合は、成長ホルモンが分泌されにくくなり、ゆくゆくは自律神経が失調してしまうこともあります。自律神経系が調子を崩すと、セロトニンといって心を安定させるホルモンが分泌されにくくなり、結果落ち込みやすく、悲観しやすくなったりします。5月病にならないように、以下のことに注意が必要です。
睡眠時間の充実を図る
勤務が厳しく、不規則な生活になり夜型になってしまった場合は、睡眠時間の充実を図る必要があります。「たかが睡眠!」とないがしろにしていたら、疲れが蓄積していき、本来うまれるはずの成長ホルモンが出にくくなり、自律神経系の調整を狂わせて、身体のあちこちに不調をきたしてしまいます。
夜十分な睡眠を確保するなら、夜に激しい運動をしたり、明るい光を浴びることはやめましょう。よく言われているスマホやPCのブルーライトの光は、脳が朝の光だと勘違いをおこし、睡眠をつかさどるメラトニンというホルモンが減少し、目が覚めてしまいます。寝る前にはブルーライトを極力減らすとともに、部屋の明かりも一段落とした照明にして過ごすことが、睡眠を充実させるコツです。
寝るという習慣をつけるには、熱いお湯でのバスタイムを過ごすのではなくて、肌より少し高い温度のお湯で、アロマキャンドルをともしながらのゆったりとした入浴を心掛けると良いでしょう。体温が上がり、その後下がった時に眠気が増していきます。そのタイミングを逃さず寝ることが、充実した睡眠時間をおくる秘訣です。
ストレス解消方法を見つける
性格的に一度失敗をすると、落ち込んだ状態から逃れられない方があります。責任感の強い方に多いのですが、失敗は反省して次回からは起こさない!とか、失敗したために次回からは頑張ろうという原動力として反省をし、自分を追い詰めるところまで反省する必要はないのです。
反省後はストレス解消のために自分の好きな事を思いっきりする!すると夢中になっていることで、深く考え込むことが少なくなり、自責の念にいつまでもとらわれることがなくなります。
食生活の改善を行う
新しい生活になると、仕事が忙しくてついつい外食に頼りがちなりますよね。しかし、忙しい時こそ食事内容には気を付けることが大切です。コンビニのごはんが続いていたり、加工食品にばかり頼っていると、食事内容がバランスよく摂れず、体の不調をきたすこともあります。野菜をたっぷり摂りビタミンやミネラルを豊富に摂取し、低脂肪で良質なタンパク質を取り入れ、偏った栄養にならないようにしなくてはいけません。睡眠不足なると、食事もないがしろになりやすくなり、食事時間も不規則になりがちですから、5月病を防ぐには自分で心掛ける必要がありますね。
5月病対策で食べ物を変えると効果がある?
5月病対策としておすすめなのが、ビタミンB、Cを摂取すること。イライラした時には、身体からビタミンCが使われてしまうので、これを補うとストレス緩和につながります。ビタミンCが多い食材は以下のものがあります。
- レモン、オレンジなどの柑橘系の果物
- キャベツ、ブロッコリー、パプリカ
野菜は生で食べるか食材を蒸して食べると、ビタミンCが壊れにくくて吸収もよくなります。疲れやすい時はビタミンBがおすすめです。食事で摂取できない時は、ビタミンBをサプリメントで摂るのもおすすめです。食事でビタミンBを積極的に摂取するなら、脂肪分の少なめな豚肉、うなぎ、胚芽米、玄米などが効果的でしょう。
まとめ
春は季節としては見どころが多い時期ですが、環境的には変化が多く、心や身体が崩れやすい時期です。ましてや新しい環境に入れば、不安や緊張から誰もが知らず知らずの間に、ストレスをためこんでしまいます。身体が悲鳴を上げているのに気付かないで過ごしていると、心まで病になってしまいますよね。4月から極度の緊張を感じ5月に突入してしまったなら、一度一人の時間を作りしっかり休むことでリフレッシュして、5月病から自分を守ることができますよ。