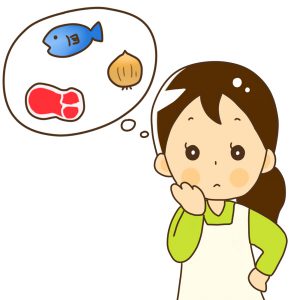いつもは元気なのに、ときどきクラクラとめまいのような症状がある。体がなんとなくだるい。こんな症状ありませんか?症状が強く出ていれば、貧血では、と思い当たるのですが、実は、隠れ貧血といわれるものがあるのです。貧血というと鉄分不足からくるのでは、とまず頭に浮かびます。鉄分は体に蓄えもあるので、不足すると蓄えから補われる仕組みになっています。なので、鉄分が不足していても、すぐに症状が現れないこともあり、いつも症状があるわけではないのです。こうなると、鉄分不足で貧血に陥っているのに、症状があまりない分見逃されやすくなり、病気が進んでしまう恐れも。
大したことではない、と見逃しのないように、貧血の症状や原因、改善方法などをみていきましょう。
目次
貧血の症状
貧血は、血液中の赤血球が不足して全身に運ばれる酸素の量が少なくなり、さまざまな症状が現れるものです。全身が酸素不足になるため、貧血の症状は、全身に現われます。
貧血は少しずつ進んでいくため、始めは、はっきりとした症状を感じない場合もあります。なんとなくだるくて疲れやすい、肩こりがある、頭痛がある、顔色が悪いなど、単なる体調不良と思い込み、気付かずに過ごしている人も多いようです。
体に出る症状
- めまいがする
- だるい
- 疲れやすい
- 動悸や息切れがする
- 吐き気
- 胃痛
- 頭痛
- 頭が重い
- 肩こり
- 顔色が悪い
- まぶたの裏が白い
- 舌の表面がツルツルしている
- 口角が切れる
肌・髪・爪に出る症状
- 肌がカサつく
- 抜け毛が増える
- 爪の色が白っぽい
- 爪が薄くて平ら、割れやすい
貧血の原因は鉄分不足だけ?
貧血の原因で、共通していえるものに、血液中の赤血球やヘモグロビンが減少して、体の細胞が酸素不足の状態になるということです。
ヘモグロビンとは
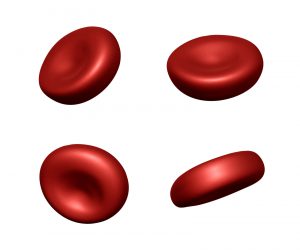
全身に酸素を運ぶ赤血球のなかには、ヘモグロビンという赤い色素が含まれています。ヘモグロビンは、鉄を含むヘムという赤い色素と、グロビンというたんぱく質からできています。ヘムに含まれる鉄は、酸素と結びつくので、酸素を体中に運んでくれます。
鉄不足の鉄欠乏性貧血
鉄欠乏性貧血は、赤血球のなかの鉄が不足することで起こります。貧血のうち、約70%がこの鉄欠乏性貧血です。
なぜ鉄が不足状態になるのかというと次のような原因があります。
食事での鉄の摂取不足
鉄はミネラルのなかでも吸収されにくいといわれていて、吸収率を考慮すると、一般の人で一日10㎎の鉄を摂らなければなりません。生理のある女性や妊婦の方は、さらに多くの鉄が必要となります。現代の食生活では、どうしても鉄の摂取量は不足しがちになっています。
鉄の吸収が悪い
食べ物から摂った鉄分は、十二指腸で吸収され、吸収率は10%くらいです。でも消化器の病気があると、吸収がよくできないことがあり、また、胃を切除した人も胃酸が出なくなり、吸収率が下がります。
体のどこかで慢性的な出血
胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんや大腸がんなどの慢性的な病気のため、出血が続くことで、貧血が進んでいることがあります。女性の生理も毎月の出血なので、貧血につながることがあります。とくに出血量が多い場合は、鉄分量が回復しないまま、また次の生理を迎えるため、貧血になってしまうこともあります。
赤血球が破壊されて起こる貧血
赤血球の寿命は約120日ですが、それよりも早く赤血球が壊されて、赤血球を生み出す能力を超えてしまうと貧血が起こります。自己免疫性疾患で溶血性貧血といいます。赤血球が壊れてできるビリルビンという黄色い色素が血液中に増えるので、黄疸症状が現われます。
また、やけど、マラソンで足の裏が繰り返し衝撃を受ける、などで、赤血球が壊れて貧血になることもあります。
ビタミンB12・葉酸不足の貧血
ビタミンB12は、赤血球が作り出されるときに働く補酵素です。また、葉酸は赤血球のもとになる赤芽球を作り出す作用があります。どちらも関わり合いながら、赤血球が作り出されます。これらの成分が不足すると起こる貧血を、異常な巨赤芽球ができることから巨赤芽球性貧血ともいいます。
食べ物で貧血を改善しよう
鉄は体内に3~4g含まれます。60%~70%は血液中に、約4%は筋肉中に存在し、機能鉄といいます。残りは肝臓や脾臓、骨髄にあり、鉄が不足すると使われるので、貯蔵鉄といわれます。生理のある女性は鉄が失われやすいため、多くの鉄を必要とします。近年の調査では、30代女性の5人に1人は血色素(ヘモグロビン濃度)が低いという報告があります。
貧血は食事で大幅に改善できる
貧血の原因のなかで多いのは、赤血球を作るのに必要な栄養素である、鉄やビタミンB12、葉酸などの不足によるものです。
栄養状態のよくなかった時代には、貧血はさほど珍しい病気ではありませんでした。その後、高度経済成長により全てが豊かな時代が訪れて、食生活も豊かになり栄養状態も以前に比べて改善されたため、貧血も減っていきました。ところが、20~25年ほど前から、再び貧血が増えてきたのです。食べるものに困ることがないかと思われる時代に、なぜでしょうか?それは、偏った食事でお腹は満たされていても、栄養が足りていないということを意識しなかったり、ダイエット志向による栄養不足などが考えられます。そういったことから、貧血を起こさないための栄養素を十分に摂ることで、貧血の予防、改善ができるといえます。
1日に必要な鉄分量と鉄分を多く含む食品
1日に必要な鉄分量
成人女性の鉄の1日の摂取基準は、生理のない人で6㎎~6.5㎎、生理のある人で10.5㎎です。
さらに、
妊婦は、妊娠初期で +2.5㎎
妊娠中・後期で + 15㎎
授乳期は +2.5㎎
女性は、こんなに多くの鉄を必要とするのです。
鉄分を多く含む食品
肉・肉加工食品
- 豚レバー・・・13㎎
- 鶏レバー・・・ 9㎎
- 牛もも肉・・・2.7㎎
貝類
- しじみ・・・8.3㎎
- アサリ・・・3.8㎎
- 赤貝・・・5㎎
野菜
- 大根の葉・・・3.1㎎
- 菜の花・・・2.9㎎
- 小松菜・・・2.8㎎
- 枝豆・・・2.7㎎
海草類
- 青のり・・・7.7㎎(10g中)
大豆製品
- 生湯葉・・・3.6㎎
- 納豆・・3.3㎎
- 生揚げ・・・2.6㎎
(100g中に含まれる量)
肉類や貝類などの動物性食品に含まれる鉄をヘム鉄といい、野菜などの植物性食品に含まれる鉄を非ヘム鉄といいます。
ヘム鉄は、非ヘム鉄に比べて吸収されやすい形になっているので、効率よく鉄が摂れるといえます。お料理にどんどん取り入れていってください。
鉄分の吸収を助ける栄養素は?
吸収率で劣る非ヘム鉄ですが、日本人は、もともと野菜や海藻などに含まれる非ヘム鉄から鉄を多く摂ってきました。鉄の吸収をよくする食品と一緒に摂ることで吸収率を上げることができます。
ビタミンC
ビタミンCは、鉄を腸から吸収されやすい形に変えてくれる働きがあります。小松菜や海苔、大豆製品などの非ヘム鉄を多く含む食品は、ビタミンCを含む食品と一緒に摂ることで鉄の吸収を効率的にすることができるのです。
ビタミンCは、野菜や果物に豊富です。野菜では、赤や黄色のピーマン、菜の花、ブロッコリー、青菜類などに多く含まれます。果物では、柿、キウイフルーツ、いちごなどに豊富です。
ビタミンCは、水に溶けやすく、熱や光に弱く、酸化しやすいので、保存や調理の際に失われやすく、鮮度のよいものを新鮮なうちに食べることがポイントです。
貧血によい栄養素は他にも
貧血予防、改善のために重要なのは、鉄分を摂ることですが、それだけでは足りないことを知っていますか?
大切な役割を果たすのが、ビタミンB群です。
ビタミンB12
ビタミンB12は、ミネラルの一種のコバルトを含み、深紅の結晶になるため、赤いビタミンともいわれます。
赤血球は寿命が短く、新しく作り変えられています。ビタミンB12は赤血球のヘモグロビンが合成されるのを助ける働きをもっています。葉酸と関わって作用しますが、どちらが不足しても悪性貧血を引き起こしてしまいます。
ビタミンB12は、微生物によって作り出されるため、動物性食品にしか含まれていません。レバーやハツなどの内臓に多く含まれ、アサリやしじみ、カキなどの貝類にも豊富です。
葉酸
葉酸はビタミンB群の一種です。新たな赤血球が正常につくり出されるときに不可欠の栄養素です。赤血球のもとになる赤芽球を作り出すのに働き、造血のビタミンともいわれます。
葉酸は、ほうれん草から発見されたビタミンで、野菜や果物に豊富です。菜の花、枝豆、モロヘイヤ、ブロッコリー、ほうれん草など緑色の野菜にたっぷり含まれています。動物性食品では、レバーに非常に多く含まれていて葉酸の宝庫ともいえます。
ビタミンB6
ビタミンB6は、赤血球をつくるときに欠かせない栄養素です。肉類では、レバーや鶏肉に多く、魚介類では、マグロ、カツオ、鮭、サバ、サンマなど、日頃目にする魚に多いですが、とくに生魚を食べると多く摂取することができます。
まとめ
この飽食の時代、栄養不足になることなどないと思われるのですが、貧血が増えているのですね。食べ物があふれているからこそ、偏食に陥って栄養がかたよってしまうなんて、皮肉なものです。食生活を見直していき、栄養バランスよく食べることが大切です。